OJTチャンネル導入企業様 紹介
■株式会社山川機械製作所
平塚市に工場を構える株式会社山川機械製作所様は、創業70周年を迎える製造業社です。金属部品加工や産業設備機械の設計・製作をはじめ、航空機、半導体、液晶ディスプレイ、通信計測機器や石油掘削等幅広い分野で事業を展開されております。

株式会社山川機械製作所
小川敦社長
■株式会社山川機械製作所様の動画配信システム導入事例
平塚市にある株式会社山川機械製作所様は、航空機、半導体、一般産業機械など、幅広い分野の部品加工や機械製作を行っています。創業70年を迎え、「小さくてもキラリと光る企業」を目指し、グループ単位で改善などの取り組みが進められています。こうした活動の発表や教育、技術伝承には動画が使われており、OJTチャンネルをご利用いただいています。
【導入前の課題】
・コロナ禍の3密回避により、社員全体で視聴していた全体昼礼などの視聴が難しくなった。
・現場の技術はカン・コツの部分が多く、無意識に行っているものもあるため、伝承が難しかった。
・機械の操作方法がわかりにくいことがあり、手順書を見るのも時間がかかっていた。
【導入後の成果】
・OJTチャンネルを導入していたことから、動画配信・分散視聴がスムーズに進み、継続して活動を続けることができた。
・動画に撮ることで技術を残すことができるうえ、新人とベテランとの比較で作業のポイントが明らかになった。
・機械本体や手順書にQRコードを貼り、動画を見てすぐに理解できるよう改善した。
― OJTチャンネルを導入されたのは、コロナがきっかけですか?
当社はコロナ前から動画の可能性に注目し、全社にWi-Fi環境を整えていました。コロナ禍で動画の必要性が高まりましたが、そういった素地があったからこそすぐに切り替えられたといえるでしょう。
弊社は、プレイングマネージャーシップに則り、グループで業務活動に勤しんでおり、「ZY20」と称する改善、5S活動をグループ単位で行っています。各グループのマネジメント、リーダー、フォロワーは様々なことを学ぶ必要があるため、毎月、研修動画を視聴しつつ、改善活動を行い、それらを繰り返すことで会社全体の統率が取れるようになりました。研修をオンラインで配信することで、講師が何回も講義を行う必要もなく、好きなタイミングで繰り返し同じ内容を社員全体で学ぶことができるのが良いと思っています。
また、コロナ禍で社員全体が集まることが困難になってしまった際も、全体昼礼等を「OJTチャンネル」を使って人数を減らして分散視聴することで、それまでの活動を切れ目なく続けることができました。
― OJTチャンネルでは、どんな動画をアップロードしていますか?

実際の作業をアップすることが多いですね。慣れていない人とベテランでは、かなり力量に差があります。それを動画に撮って比較することで違いがよくわかり、技術の伝承に活かせると考えました。
同じ作業をベテランが行うと速いので、動画の中にベテランと新人の動画を入れ込み、倍速を変えて同じ時間で終わるように調整しています。映像での比較は、教育の場面で使うと効果が高いです。手取り足取り教えてあげても、自分ではどう動いているのかわかりにくい。しかしビデオに撮ると客観的に見えてくるのでよくわかるようです。実際に「こんなことしていたんですね」と気付いた人もいました。また、作業手順書は右利きを基準に作られているため、手順書に従っていても、左利きの人とは動きが違ってくることもわかります。
― 動画の撮影や編集はどうしていますか?
“社内で複数のスタッフが撮影しています。はじめはビデオカメラも用意しましたが、操作手順を覚えなくてはいけません。「編集をどうする?」といった問題も出てきて、やはり使い慣れたスマートフォンが便利だろうということになりました。
編集も撮影者が行います。最初は見よう見まねでしたが、やってみたら結構できるものですね。”
“れぞれ撮影者がスマートフォンで動画を編集して、OJTチャンネルの「みんなでとる」アプリからそのままアップできるところがいいですね。
ある程度たまってきたらカテゴリーに分けてフォルダにまとめたほうが探しやすいので、その作業は事務担当が行っています。”
― 皆さん、撮った動画を自由に加工されているのですね。
“事務で制作したものはポップでかわいい感じですし、動画制作に詳しい人はユーチューバーっぽい編集をするなど、個性的に仕上げる人も出てきました。部署によっては技術的なことを多く入れていますし、アバターに読ませて音声を入れているところもありますね。
編集も撮影者が行います。最初は見よう見まねでしたが、やってみたら結構できるものですね。”
― QRコードも活用しているとお聞きしました。
“ハンディターミナルなどの使い方を、動画でも見られるようにしています。手順書だけでは、技術的な部分で分かりにくいことがあります。そんなとき、機械や手順書にQRコードが貼ってあれば、すぐに動画で確認することができてとても便利です。
編集も撮影者が行います。最初は見よう見まねでしたが、やってみたら結構できるものですね。”
― OJTチャンネルを導入されてよかったと思うのは、どんな点ですか?
事務所でも現場でも、一人で担当している仕事がありますよね。その人が急に休むと、「発送の仕方がわからない」など、ちょっとしたことで困ってしまう。そんなとき、作業を動画に上げていると助かることがあります。見てそのとおりにやればいいだけですから。
“もちろん全ての作業にマニュアルや指示書があるのが理想ですが、それには別の作業が伴います。動画は普段仕事しているところをそのまま撮ればよいだけなので、文章を作るよりも手軽にできます。
また、文章のマニュアルだけでは、「これは、こういうことかな?」と、解釈を間違えるかもしれません。でも、動画で見れば一目瞭然。時間はともかく、確実に同じことができるのはいいですね。”
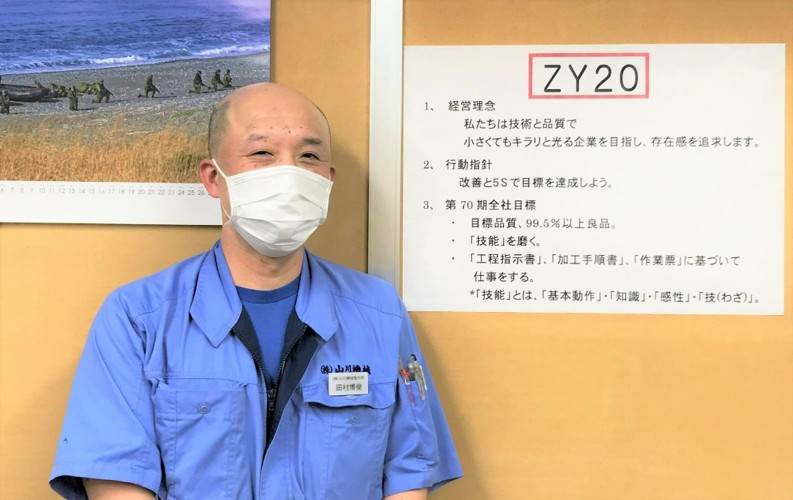
取材をお受けくださった
(株)山川機械製作所の田村様
― OJTチャンネルを導入されてよかったと思うのは、どんな点ですか?
今までは共有すべきこと、残すべきことを中心に動画を作ってきましたが、これからは、育成カリキュラムとしての利用も大切になるでしょう。ある程度そろってきていますが、さらに体系的に進めていけば、教える側の負担も軽くなります。
動画で蓄積された技術データは、私たちの大切な財産といえます。さらに加工手順を区割りするなど、見る人がわかりやすいよう整理していこうと思っています。コロナ禍以降、動画配信は当社に欠かせないものとなりました。「どんな動画をどう使えば技術を無理なく伝えていけるか」、そんな議論が全社活動「ZY20」の中で行われていけば、この先もどんどん良い方向に進んでいくに違いありません。
動画を始めてから、かつての年功だけでは考えられなかった、コミュニケーションの活性化も生まれてきました。動画に関しては年長者が若者を「先生」と呼ぶ場面も見られます。動画の制作や配信によって、グループ内のリーダーとフォロワーの良好な関係が保たれ、さらに発展していくことを期待しています。
